インタビュー(曽野綾子さん)
● インタビュー ● 「私日記〈5〉私の愛する妻」 曽野綾子さん
掲載:2007年
20160927close/BOOKSERVISEより転記(テキストのみ)
曽野 綾子さん
プロフィール
1931年、東京生まれ。
1953年、三浦朱門氏と結婚。
1954年、聖心女子大学英文科卒業。
1979年ローマ法王庁よりヴァチカン有功十字勲章受賞。
1993年、恩賜賞・日本芸術院賞受賞、同会員。
1995年、「日本財団」会長就任(2005年まで)。
2003年、文化功労者。著書多数。
作家生活53年。そして、これから。
小説、ノンフィクションを通して「人間」を見つめ、
戦争と平和、貧困、教育、宗教、うつなどをテーマに
、幅広い執筆活動を続けられてきた曽野綾子さん。
「作家」という生き方はどんなふうに始まり、どこへ向かうのか。
――子どものときにお母様から、日曜日ごとに作文を書くように指導されたとか。
母は、将来ふたつのことが必要になるから、と言っていました。ひとつは、いいラブレターを書かなければならないから。ふたつ目は、結婚相手が事業に失敗して一家心中する前に、いい借金の申し込みの手紙が書けるように。
母らしい言い方です。ラブレターというのは、人間関係を保ち、こじれても修復することができる手紙という意味でしょう。そして、生活苦になっても合法的に――盗みなんかじゃなくて――生きていけるようにということ。母はやや悲観的人間でしたから。
――子どもにとっては、かなりのノルマです。
その当時は、作文とともに、ピアノと踊りもやらされました。ピアノは好きになれなかった。踊りは戦争のごたごたの頃、名取りになりましたが上手いというわけではありません。でも盆踊りならすぐ加わりますよ。
結局、強制されて定着する確率は半分ぐらい。でも子どもの教育というのは、強制でいいと思っています。言葉を覚えるのも、社会のルールを身に付けるのも、最初は強制からです。いずれイヤなものは自分で止めますから。
最初は苦痛だった作文は、次第に楽しくなってきました。そして小説家になろうと思ったのが小学校6年生のとき。高校時代は同人誌を出す費用をつくるために民放ラジオに投稿をしていました。かなり採用されましたよ。家で夕ご飯のあと、原稿用紙10枚ぐらい書くのは平気でした。
――23歳で『遠来の客たち』が芥川賞候補。それ以来、行き詰まったことは?
主人(三浦朱門氏)は「そのうち大きな壁にぶつかる」と予言していましたね。「いまの若書きの勢いだけでは、続かなくなる」と。
実際、30代の7、8年間は書けずに、不眠症・うつ病になりました。その危機を脱するのは『無名碑』を書き下ろしたときからです。ダムやアジア・ハイウェーの建設現場で働く技術者たちの人生を書きました。土木の勉強もし、現場もたくさん見せてもらいました。土木の仕事は自然破壊と悪く言われたりもしますが、彼らは今日の日本を造った人たち。その苦労には感謝と尊敬の念があります。
私は今でも「足」で書くのです。書斎の中だけで暮らしていては書けない。『無名碑』以来、書くことがなくなる、ということがなくなりました。
――「日本財団」「海外邦人宣教者活動援助後援会」の仕事で発展途上国へよく行らっしゃいますね。
私たちに託された寄付金が、申請通りに正しく使われているか確認しに行きます。貧しい社会には、泥棒が多いですからね。文化も違う国です。日本人が考える“いい人”ばかりということはあり得ません。あるとき、優秀な女性を看護婦にするための費用を出してほしいという話がありました。それには、必ず報告を出してもらうこと、お金は本人に渡すのではなく看護学校に直接振り込むことを条件にしました。彼女たちはきっと“貧しい親戚”に渡してしまいますからね。そうしたら、学校の学長が持ち逃げをしてしまった・・・。失敗例は少ないですけれど。
実は、私は一日中家にこもっていたいほうなのですが、マッサージをしてくれる方に言わせると、東京にいるときよりアフリカに行くと体が良くなって帰って来るそうです。現地では、生きるための構えが要る。食べ物、害虫、悪路、泥棒、マラリアなど様々な危険を回避するために、頭も体も使います。そして、生きるというのは何かを考えさせられる。アフリカは偉大な教師、と私が言うのはそういう意味です。
――『私日記』が続いています。そこで描きたいことは。そして今後のご予定は。
『私日記』では、小さな平成の裏面史を綴りたい。イワシをいくらで買ったかとか、何に怒ったかということ、フジモリ元大統領が我が家にいらした記録もあるし、足首の骨を折ったことはまあドジの最たるものですね。『私日記』の「私」は、私小説の「私」。自分の回りの卑小なものを通して、時代を書き留めたいと思っています。
骨折の治療には時間がかかりました。療養を兼ねて訪れたのが、イタリアのアバノ。ここが今度の小説『アバノの再会』の舞台になりました。この小説は、純粋な恋愛小説。大人の恋です。もうSEX小説はたくさん(笑)。セックスなんて子どもみたいなことは書かないことにしたの(笑)。
小説家は人間の「悪」を見ることが役目だと思っています。「悪人」や、世間が「悪」だと言う事柄を書いていきたい。私は絵を描かないのですが、光というのはどうやって描くかというと、影を描けばいいんですね。闇を書くことで人間の光を書いていきたいと思っています。


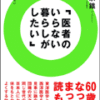




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17d6d998.a7c60c45.17d6d999.0f382150/?me_id=1313634&item_id=10000106&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbell-hammer-shop%2Fcabinet%2F04483050%2Flsbhg%2Fimgrc0073910752.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません