インタビュー(濱田美里さん)
● インタビュー ● 「濱田美里の季節の手仕事帖」 濱田美里さん
2008年
20160927close/BOOKSERVISEサイト転記(テキストのみ)
濱田美里さん
プロフィール-
1977年、広島県の下蒲刈島生まれ。
上智大学卒。在学中から世界の民族料理、日本の郷土料理を訪ね歩く。新聞、雑誌、TV出演など幅広く活躍中。国際中医薬膳師の資格を持ち、現在も中医学の勉強中。
台所に人を呼び込む本。
台所には、楽しさがある。驚きがある。健康がある。季節がある。
もっと気軽に手作りを、と本を通して呼びかける
料理研究家・濱田美里さんにお話を伺った。
――濱田さんの「食」の原点はどこにあるのでしょうか。
広島県の小さな島で生まれました。美味しいお魚や裏庭で取れた野菜、そして毎日家族でご飯を食べてきたことが原点だと思います。料理を作るのは、母と祖母。私は出来上がったときに、鈴を鳴らして「ご飯よ~」と家族を集めるのが役目でした。それが、嬉しくて、嬉しくて。私がみんなにふるまうような気持ち。今もその延長のような気もします。
実は十代の頃はロック歌手になろうと思っていたんです(笑)。親から猛反対されましたが、それでも、大学を卒業したらプロになる、それで食べていく、20歳までにはデビューしようと本気で考えていました(笑)。でも才能のなさに気付き、断念。しばらくは悶々としていました。これから何で自分を表現したらいいのか、どうやって生計を立てていくのか…。その中で考えたことは、美しいと思ったものを信じて生きていきたい、ということ。私が美しいと思うもの、それは、子どものときに食べたトマトの味と毎日の晩ご飯でした。「料理」なら五感全部を使って表現できると思いましたね。
――大学四年のとき、料理で“ライブ”を企画したとか。
レストランを借り切って、時間は二時間。みんなに私の料理を食べてもらうイベントです。まだレパートリーもないのに無謀です(笑)。やはり手助けしてくれる方が必要で、ある有名なホテルに電話をしてシェフの方にお話ししたら、ありがたいことに応じていただけた。会場の下見も付き合ってくださり、見兼ねたのか、僕が作りましょうか、とまでおっしゃる。それはさすがにお断りしましたが(笑)。
器屋さんにもご厚意でたくさん器を貸していただきました。縁に恵まれましたね。その後もその方たちにはお世話になり、職業としてやっていくための具体的なアドバイスをいただきました。
ちなみに、そのときのお客様は全部で27名。友達だけでなく、批評が欲しかったので食の専門家の方にも来てもらいました。会費は3000円、学割2500円でした。
――その後は順調に、料理家の道を歩まれた?
学校出立てのフリーの料理研究家に、仕事の話などそう来るわけがなく、本当にヒマで貧乏でした。服も買えないし、実家に帰ってはタンスをあさり、祖母の着物をもらって着ていました。着物を着る習慣はそれ以来。着物姿だと大和撫子のように思われますが、事情はまったく違います。
料理の世界に入ったとはいえ、私には基礎がありませんでした。そもそも料理というのは自己表現の手段ではないし、食べてくれる人があって成り立つもの。そこからまた悩みが始まったわけです。私の料理って何だろう、と。
――師匠と呼べる方はいるのですか。
インドからアフリカへ旅行したことがあります。そのとき親しくなった友人に「土産とカメラのフィルムを実家に届けてほしい」と頼まれて、ご実家のお母様を訪ねたときのこと。「あなたは何をしているの」と聞かれ「料理です」と答えたら、「それでは、ピンからキリまで知らなければね。勉強のために行ってみたいレストランがあれば一緒に行きましょう」とおっしゃる。初対面で、です。ヒマな私はそのお宅へ毎週アルバムの整理のアルバイトで伺うことになったのですが、ある日、料理を作っていたら、出来上がる寸前に二階から下りていらっしゃって「香りが悪い!」。そして、パパッと直された。見違えるように美味しくなりました。私はこの人を師匠にしようと決めましたね。
このお宅で、冬になれば沢庵を漬けて、梅の季節には梅干し作り。アフリカで別れた友人が「美里という人が訪ねるから料理を教えてあげて」とお母様に電話を入れておいてくれた、ということを知ったのは通い始めて一年ほど経ってからでした。「見ず知らずの人に?」というお母様に「それは日本文化を伝えることだよ」と友人は言っていたそうです。
結局三年ほど通い、たくさんのことを教えられました。
――どういう料理研究家でありたいと思いますか。
先人の料理の知恵を伝えたい。いま書き留めておかなければ途絶えてしまう料理があります。郷土料理の取材をライフワークにしているのは、そんな焦りがあるからです。
でも、今は伝えるだけでは済みません。ハードルは高くなっていると思います。まず、台所に帰って来てもらわないといけない。手作りの楽しさ、驚き。そして、切ったり煮たりする中に、季節を感じる喜び、素材の持つ力強さなどもレシピに込めて、“料理の間口”を広げていきたいと思います。
「料理人」は作るプロ。誰にもできない料理を作って食べてもらう人。「料理研究家」は作ってもらうプロ。誰もが作れるレシピを考えて作ってもらう人。私はそう思っています。これからも、どんな人が作るのか、どんな環境で作るのか、想像力を働かせながらレシピを開発し、本を作っていきたいと思います。

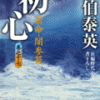





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1652043a.bfad16c9.1652043b.180eaa49/?me_id=1213310&item_id=20034188&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6775%2F9784099416775_1_31.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17d6d998.a7c60c45.17d6d999.0f382150/?me_id=1313634&item_id=10000106&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbell-hammer-shop%2Fcabinet%2F04483050%2Flsbhg%2Fimgrc0073910752.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません