インタビュー(小松左京さん)
● インタビュー ● 「日本沈没」 小松 左京さん
2007年
20160927close/BOOKSERVISEサイト転記(テキストのみ)
小松 左京さん
プロフィール
1931(昭和6)年、大阪生まれ。
京都大学文学部卒(イタリア文学専攻)。日本推理作家協会賞受賞の『日本沈没』をはじめ著書多数。
「日本人」を考えたくて書いた『日本沈没』。
1月19日に、『日本沈没』のDVDが発売された。
昨年公開され大きな話題となったこの作品は、二度目の映画化。
なぜいま再び「日本沈没」なのか、科学の発達はSFを変えるのか、日本のSF界を常に牽引してきた小松さんにお話を伺った。
2006年制作映画『日本沈没』はご覧になっていかがでしたか。
まずCGの技術の進歩に驚きました。33年前には模型をつくって撮っていたシーンが今回はほとんどCGですからね。スケール感が出ました。大地真央さんの女性大臣の顔がクローズアップになって演説するシーンなど、私には新鮮でした。
『日本沈没』がいま再び注目される理由をよく聞かれるのですが、作者としてはわかりませんね。インターネットでボーダーレスの社会になっていながら、一方では、宗教的な対立、民族対立、テロなど、「国家」や「国家と個人」の問題を考えさせられる事態が多く起きている。また、「阪神大震災」などで自然災害に対する関心も高まった。そんな背景があるのかもしれません。
『日本沈没』は、当時の“浮かれた”日本に警鐘を鳴らそうと思って書かれたとか。
敗戦から20年足らずなのに、高度成長に戦争を忘れてしまったかのような日本人に警鐘をならすという側面もありましたが、それだけではありません。戦争の末期に「本土決戦」「一億玉砕」といわれ、中学生だった自分は死を覚悟した。それが天皇の終戦の詔勅で死なずにすんだ。また、2発の原子爆弾で日本は無差別大量殺戮の対象にもなった。そんな体験をしながら生き延びた日本人として、もしあのまま「一億玉砕」していたらどうなっていたのか、を考えてみたかったのです。その思いは処女作の「地には平和を」にも表れています。
そう思っているとき、竹内均先生の「地球の科学」を読み、ウェゲナーの「大陸移動説」が復活してきたことを知り、これを使えばどの国も敵にすることなく、日本の国土を日本の国民から失わせることができると「日本沈没」を思いついたのです。
1973年の『日本沈没・第一部』から『第二部』まで33年。世界情勢の変化で『第二部』の構想は変わりましたか。
91年のソ連の崩壊以後、世界の地図が大きく変わりました。共産主義の脅威がなくなった代わりに、イスラム原理主義の問題が表面化してきた。70年代には、国土を失った日本人が世界でどのような扱いを受けるのか、ユダヤ人のように時には嫌われながらも民族のアイデンティティーを失うことなく図太く浸透していくのか、それとも、それぞれの地域に溶け込んで「日本人」は消滅していくのか――。そのときに私が考えたのは、日本の文化を継承しながらも「地球人」として生きる考え方をもてるようになれないだろうか、ということです。そこで「コスモポリタリズム」ということを、第二部では考えていました。谷甲州君とは、いっしょに議論してきたので、背景の世界情勢は変わりましたが、今回の第二部でも、その考え方は入れました。
近年の科学技術の発達は、SFをどう変えるのでしょうか。
SFは、科学技術が発達したからといって変わるものではありません。ただ、科学技術の発達によって広がる知識世界は、新たなイマジネーションを刺激する事は確かです。
また、科学技術の発達によって、人間の社会、人間関係がどのように変わるのか。それを見つめ捉えて考え、多くの人にわかりやすい物語を作るのが、SF作家です。科学が解明していく世界が広がると、SFの創造の余地が少なくなって、SFがつくりにくくなるという見方もありますが、SF作家ならば、シリアスな中にファンタジーやユーモア、風刺、パロディによって想像力をふくらまさなければならない。それだけ旺盛な知識の「咀嚼力」が求められるという意味では、大変かもしれませんね。
いま考えていらっしゃるテーマは。
体力的に新たな作品を執筆することはできませんが、問題意識としては、この宇宙に地球という惑星ができて生命が誕生し、進化して「人類」という知的生物にまで到り、「文学」を生み出したことの意味を問いたいですね。「宇宙と生命」「宇宙と知性」「宇宙と文学」について、共に考えてもらいたい。
『小松左京全集完全版』(城西国際大学出版会)の刊行が始まっています。
ありがたいことと思っています。特にノンフィクションを読み直してもらうことは、全集でないと難しいので、嬉しいですね。こうして一覧すると自分でも忘れている作品が思い出され、自分の45年間にわたる作家人生を振り返ることにもなり、感慨深いものがあります。
※このインタビューはメールで質問にお答えいただいたものをまとめました。





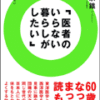

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1652043a.bfad16c9.1652043b.180eaa49/?me_id=1213310&item_id=21609904&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fcabinet%2F4809%2F9784089084809_2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17d6d998.a7c60c45.17d6d999.0f382150/?me_id=1313634&item_id=10000106&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbell-hammer-shop%2Fcabinet%2F04483050%2Flsbhg%2Fimgrc0073910752.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません