陰謀論・構造論?メディア重く、弁護士団メンバーも???
テロリスト山上徹也被告の公判が始まった。この裁判は「裁判員制度の対象外」であり、メディア報道も軽い。また弁護団も社会的発言の高い弁護士ではなく、淡々とした裁判のように感じる。
2022年7月、安倍晋三元首相が奈良市で銃撃され死亡した事件は、戦後日本の政治と宗教、司法と報道の関係を根底から揺るがす衝撃をもたらした。だが、事件から3年以上が経過した今、私たちは本当に「全体像」に近づけているのだろうか。むしろ、あまりにも整いすぎた構図と、あまりにも静かな報道環境に、違和感と警戒心を抱かざるを得ない。
この違和感は、単なる陰謀論ではない。むしろ、構造的な沈黙と情報の非対称性に対する市民的な懐疑である。
裁判の非公開性と弁護団の静けさ
山上徹也被告の裁判は、殺人罪を争わず、銃刀法違反の一部技術的争点と情状酌量に絞られている。裁判員制度の対象外とされたことで、市民の目が届かない非公開の場で審理が進行している。これは、重大事件における司法の透明性という観点から見て、極めて異例だ。
さらに、弁護団の構成にも疑問が残る。奈良弁護士会所属の3名で構成されているが、いずれも全国的な人権派ネットワークには属しておらず、宗教と政治の構造的関係に踏み込むような発信は見られない。なぜこのような弁護団が選ばれたのか。なぜ、より強い発信力を持つ弁護士が関与していないのか。不可解である。
報道の沈静化と「個人の動機」への矮小化
事件直後、旧統一教会と政界の関係が連日報道されたが、数週間で急速にトーンダウンした。その後は、山上被告の家庭環境や読書傾向といった「個人の動機」に焦点が移り、構造的な問題提起はほとんど姿を消した。
これは偶然だろうか。あるいは、報道機関が政治的圧力や広告主の影響を受けて、「報じない自由」を行使している結果なのか。記者クラブ制度やメディアの系列化を考えれば、報道の横並びと沈黙は、構造的な必然とも言える。
「陰謀論ではなく構造論」で考えるべき理由
私たちは、誰かが裏で糸を引いているという単純な陰謀論に陥るべきではない。だが同時に、「構造的に語られないようにされている」現実から目を背けるべきでもない。
- なぜ裁判は市民から遠ざけられたのか
- なぜ弁護団は構造批判を行わないのか
- なぜ報道は急速に沈静化したのか
- なぜ政治家の責任は問われないのか
これらは、制度と報道と司法が連動して「個人の動機」に収束させる構造が存在するのではないか、という問いである。
終わりに:触れてはいけないものなのか?
「陰謀論」として片付けられることを恐れて、疑問を口にすることすらためらう空気がある。だが、構造的な沈黙に対して疑問を持つことは、民主主義社会における健全な懐疑心である。むしろ、そうした問いを封じる空気こそが、構造の一部なのかもしれない。昨今のオールドメディアと言われる報道機関も、安倍晋三元首相暗殺についてはあっさりした感が強く感じます。
私たちは今こそ、「語られないこと」にこそ耳を澄ませるべき時にいる。
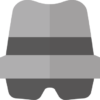


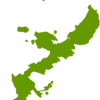
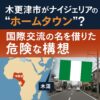



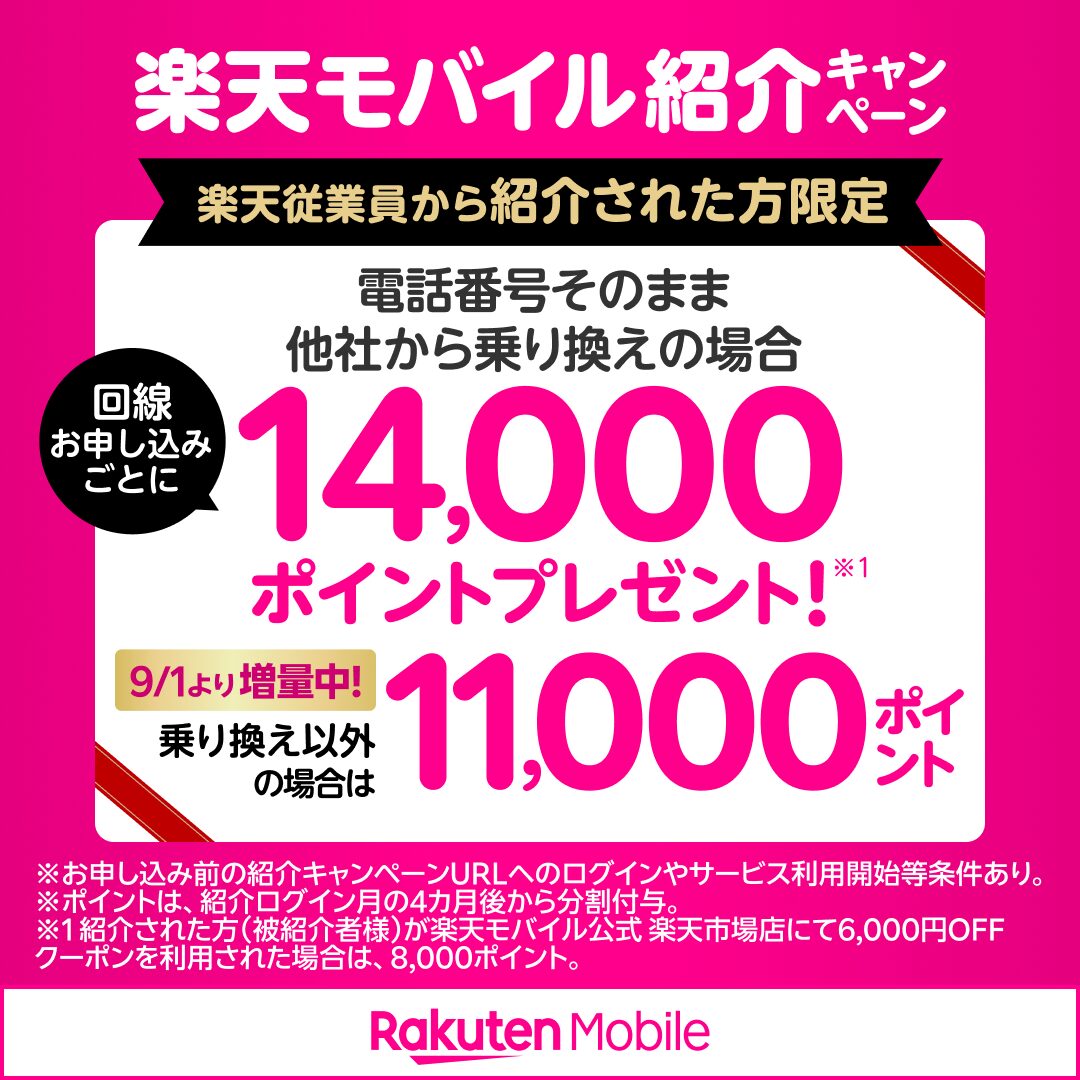
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17d6d998.a7c60c45.17d6d999.0f382150/?me_id=1313634&item_id=10000106&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbell-hammer-shop%2Fcabinet%2F04483050%2Flsbhg%2Fimgrc0073910752.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



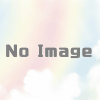



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません