ミヤネ屋 三輪記子弁護士、小野田議員ブロック続出?
ブロックは「情報の非公開」ではなく「相互作用の制限」であり、何よりオールドメディアがそのものです。
小野田紀美議員に難癖をつける体質にしか取れず、まず自分たちの偏向報道や報道しない自由を恥じるべきではないか?
ブロック機能は「市民の知る権利」や「表現の自由」を阻害するか
2025年10月29日放送の情報番組『ミヤネ屋』(日本テレビ系)にて、弁護士の三輪記子氏は、経済安保担当大臣である小野田紀美議員のSNS運用について次のように言及した。
「私の友人とかでも、X(旧Twitter)でブロックされているという人が続出していて、市民の知る権利にも応えていく大臣であってほしい」
この発言は、SNS上でのブロック機能が「市民の知る権利」や「表現の自由」を阻害する可能性を示唆するものであり、視聴者やネットユーザーの間で議論を呼んだ。しかし、ブロック機能の技術的性質や憲法上の権利構造を踏まえると、この主張にはいくつかの誤解が含まれている。本稿では、SNSのブロック機能が憲法上の権利を侵害するものではないことを論理的に整理する。
1. ブロック機能の技術的性質
SNSにおける「ブロック」とは、特定のアカウントからの通知、返信、引用投稿などのインタラクションを制限する機能である。ブロックされた側は、相手の投稿に対して返信や引用ができなくなるが、投稿自体の閲覧は可能である。つまり、情報へのアクセスそのものが遮断されるわけではない。
この点において、ブロックは「情報の非公開」ではなく「相互作用の制限」に過ぎない。したがって、情報の受信や閲覧を妨げるものではなく、「知る権利」の根幹を侵害するものとは言えない。
2. 憲法上の「知る権利」と「表現の自由」
日本国憲法第21条は「表現の自由」を保障しており、これには情報の発信・受信の自由が含まれると解釈されている。ただし、これは国家権力による不当な制限を禁じるものであり、私人間の関係においては直接的な適用はない。
また、「知る権利」は判例上、報道機関の取材活動や情報公開制度の文脈で語られることが多く、SNS上の個人間のやり取りにおいて当然に保障される権利ではない。公職者が情報発信を行う場としてSNSを選択した場合、その内容は原則として公開されており、ブロックされていても閲覧可能である以上、「知る権利の侵害」とするのは論理的に飛躍がある。
3. 表現の自由は双方向ではない
「表現の自由」は、発信者が自らの意思で情報を発信する自由であり、受信者が必ず発信者に対して反論や返信を行える権利を含むものではない。SNSにおいても、ユーザーは自らの投稿に対して誰が反応できるかを選択する自由を有しており、これはプラットフォームの設計上も認められている。
公職者であっても、誹謗中傷や執拗な絡みを避けるためにブロック機能を使用することは、自己の表現空間を守るための合理的な手段であり、憲法上の権利と矛盾するものではない。
4. 誤解と感情的反応の整理
SNS上で「ブロックされた」という事実が感情的な反発を呼ぶことは理解できる。しかし、ブロックは「議論の拒否」ではあっても「情報の遮断」ではない。ブロックされた側も、他の手段で情報を取得し、意見を表明することは可能である。
また、ブロックされたことをもって「市民の権利が侵害された」と主張することは、権利概念の過拡張であり、公共的な議論の質を損なう危険がある。
結論:ブロックは権利侵害ではなく、表現空間の調整手段である
SNSにおけるブロック機能は、発信者が自らの表現空間を調整するための技術的手段であり、「市民の知る権利」や「表現の自由」を阻害するものではない。むしろ、過度な干渉や攻撃的な言説から距離を取ることで、冷静で建設的な情報発信を継続するための防御策と位置づけるべきである。
公職者によるブロックの是非を論じる際には、感情的な反発ではなく、技術的・法的な構造を踏まえた冷静な議論が求められる。
先にも述べたが、オールドメディアこそ相互作用の制限がかかっており、そこに携わっている以上、Xのブロックを批判する権利はない。
Ps.小西洋之議員やハッピー米山議員、河野太郎議員のブロックしまくりは有名ですね。
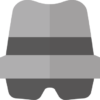






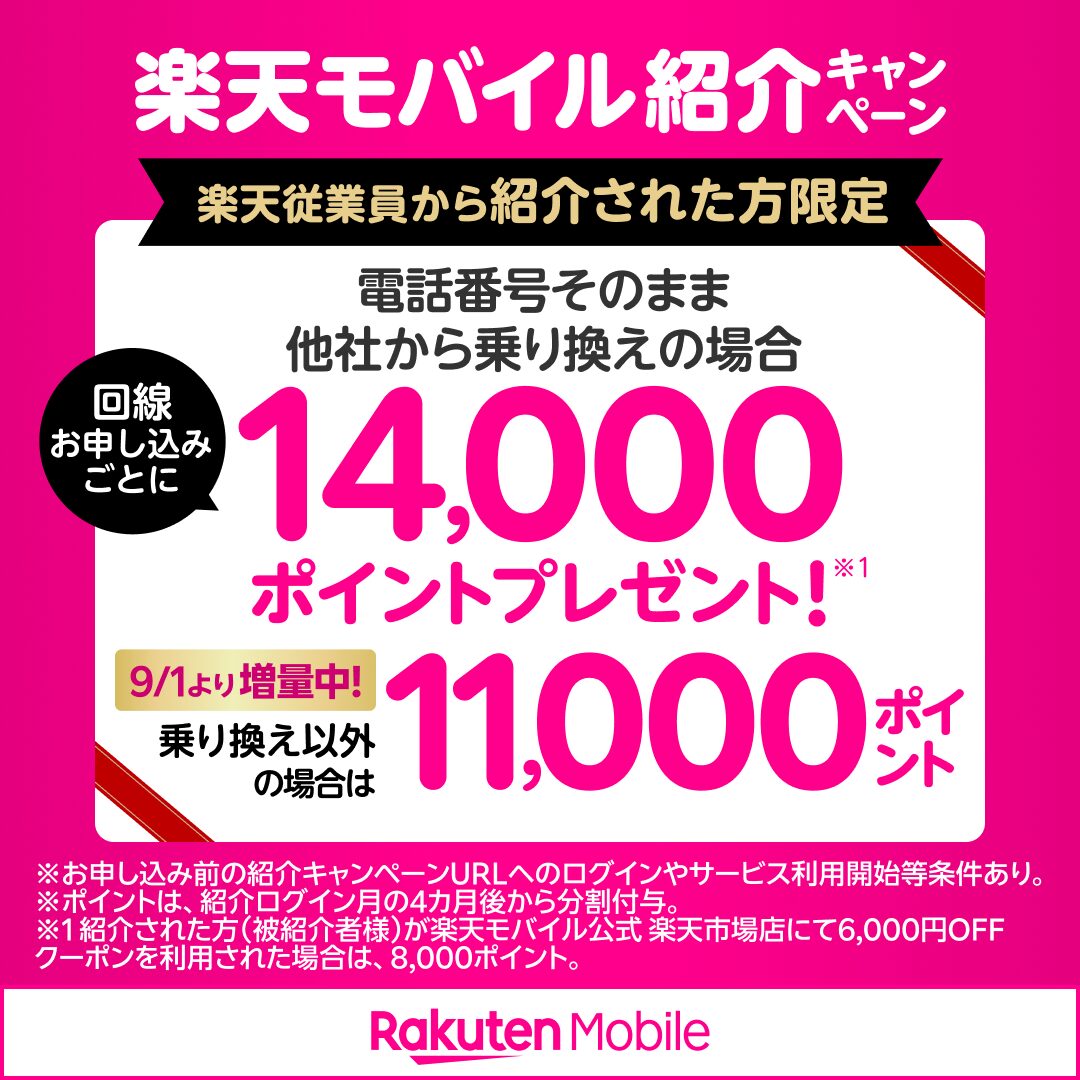
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17d6d998.a7c60c45.17d6d999.0f382150/?me_id=1313634&item_id=10000106&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbell-hammer-shop%2Fcabinet%2F04483050%2Flsbhg%2Fimgrc0073910752.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



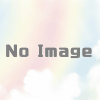




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません